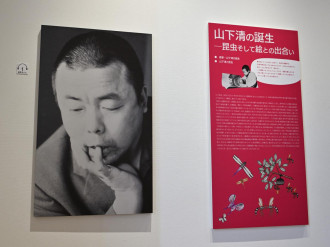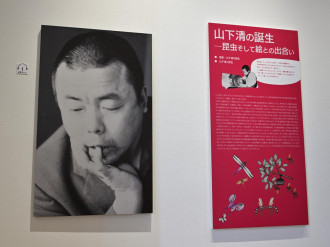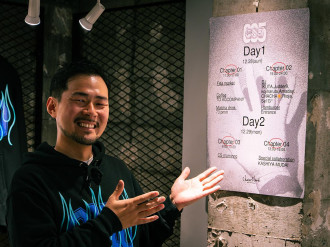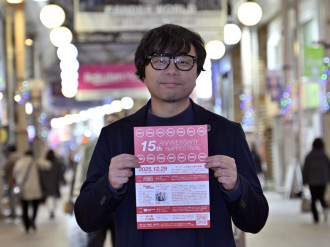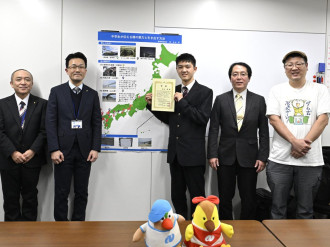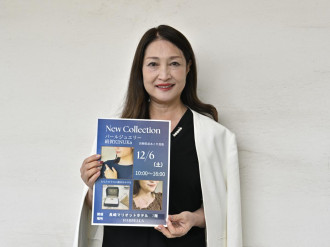「私の海藻、大きくなあれ!海藻School2024」が5月23日・24日、時津北小学校(時津町日並郷)で行われ、6年生約50人が海藻の卵を採取して苗つけを行った。
「次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる」ことを目的に日本財団が取り組む「海と日本プロジェクト」の一環。「大村湾ワンダーベイプロジェクト」の企画の一つとして一般社団法人「海と日本プロジェクトinながさき」が同校と東彼杵町立彼杵小学校で実施。「ダイビングサービス海だより」(長崎市滑石4)の中村拓朗さんを講師に招いて出前授業を行うとともに、校内で海藻の陸上養殖を行うための苗つけを行った。
昨年の総合学習で大村湾のことを学んだ児童らは「大村湾のために何かできることをしたい」とプロジェクトに参加。講師の中村さんは漁協や大学などと協力して藻場の再生や磯焼け対策など海の環境保全に取り組んできたほか、登録者28万人のユーチューブチャンネル「スイチャンネル」で水中映像を公開し、海の現状などを発信してきた。
23日、体育館に集まった児童らに中村さんは「藻場は海の生き物のゆりかごと言われるほど大切な場所だが、近年海の砂漠化・磯焼けが深刻化している。超閉鎖性海域である大村湾は周辺地域から受ける環境への影響が大きい」などと説明。「藻場再生のきっかけにしたい」と自身が取り組んできた海藻を養殖し、藻場を増やすための活動を紹介した。
児童らにアカモクとヤツマタモクが配られると、中村さんは卵の採取方法を説明。児童らははさみを使って卵の入ったさやを切り出し、採卵用のトレーに集めた。児童から「海藻についている丸い玉は卵じゃないの?」という声が上がると、中村さんは「気泡と呼ばれる浮袋で、海藻が立つために必要なもの」などと説明した。
翌24日は採取した卵の苗付けを実施。餌となる栄養分を与えるなど世話をしながら教室で飼育を行う。秋ごろに大村湾に植え付けを予定し、来年春ごろには20~30メートル規模の藻場の造成を見込むという。